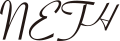新潟県内のエステティック・リラクゼーション業の社会的地位確立を目指します
 生まれてきた一人ひとりに、等しく幸はある
生まれてきた一人ひとりに、等しく幸はある
もうずいぶん前のことである。
ひょんなことから、見ず知らずの男女10人ばかり集まる酒宴に誘われた。小さな部屋に皆、膝を突き合わせて座り、各々の仕事の楽しさ辛さ、家庭の中での女性の役割や自由度について語り合った。私は皆さんより少々年下だったので、概ね聞き役にまわった(はずだ)が、オトナの男女の語らいは凛々しく、羨ましささえ感じたものだ。
その中に髭をたっぷりとたくわえた、初老の男性がいた。私が物書きと知ると男性は後日、連絡をくれたのだが、その依頼が変わっていた。
「遺書を書きたい、手助けしてほしい」という。
遺書、の響きに驚いたが、書き上げたら死のうとか、病気療養中ではないと説明され、お受けした。先の宴会での高揚感や、芸術家肌の男性への好奇心も、私の背中を間違いなく押した。
蓋を開けてみれば、それは遺書というより半生記の色が濃く、男性に関わったある人への、怨恨を長々と書き綴った手紙であった。やり方としてはまず、ベースとなる文章を男性が書き、それを私が整理し、男性の意を汲みながら強弱を付けた表現にしていく。
数回の面談と原稿用紙のやり取りで終えそうな仕事であったが、原稿の受け渡しをしにご自宅へ伺ううち、困惑した。
テーブルに着くときまって男性は、「はい、これ原稿」と、新聞の折り込み広告を差し出した。数枚の裏白チラシにはびっしりと、ボールペンの文字。「拝見します」とその場で読み始めるのだが、訪問3回目に異変が起きた。私の手ですでにPC出力し、男性に渡してあるはずの文章パートが、手書きで延々と書き換えられていたからである。
「昨夜ね、考えていたらどんどん書き進んじゃって」
お茶を煎れながら、男性が言う。
私の表現がお気に召さなかったのかもしれない。そう思って手直しをし、また数日後にお邪魔すると、再び同じ箇所の直しが提出された。
「ぼく独り暮らしでしょ。夢中になって夜、書いちゃうの。色々思い出してね」
私は溜め息を悟られないよう、持ち帰った。まじまじと読んでも、あまり変化はない。それでも、1行でも新しい要素があれば書き足して、清書をする。
さすがに次はないだろうと訪ねたら、やはりそのくだりはあった。原稿はすでに、400字詰め用紙で結構な枚数になっている。まったくの他人事ではあるが、清書をする私もヒリつくような争いごとが、足踏み状態で繰り返されることに気が遠くなった。そしてふと、思い付く。言いづらいし認めたくない。だが訊いてみた。
「……あの、もしかして……これ、お酒を飲みながら書いてます?」
男性は掛けていた老眼鏡を、指で引き上げた。続けて「そうだよ」と、こともなげに言った。
「だって飲まなきゃ書けないじゃない」
その日、「清書原稿はちゃんと読み、同じ直しはしないでください」とキッチリ頼み、そののち数回で校正終了としてもらった。
長い長い、誰かへの手紙は間もなく郵送され、男性はずいぶん留飲を下げたようである。
酒は魂に潤いをあたえ
悲しみをしずめ
優しい感情さえも呼び起こす
哲学者ソクラテスは酒についてこう詠った。あの男性にも酒を飲みながら、何度も同じシーンを振り返る必要があったのかもしれない。――私も、彼と似た年齢になった。
*
新聞や書籍に関わる仕事では、左党であれば当たり前に飲んで書いていた時代がある。東京での話だが、私の若い時分は男性上司と一緒にランチに行けば、大体がビール付きだった。モーレツに書き、モーレツに飲むという、昭和の余韻とでもいおうか――まぁ、そんな私でも、この男性との一件で心に誓った。
「私は飲んだら、絶対に書きません!」

酔いに任せ、リラックスして好きなように書く。アイデアも次々湧いて「もしかしたら私って才能アリ?」と舞い上がるが……翌朝、読み返した時のガッカリ感は相当なもの(笑)。

石坂智惠美(いしざかちえみ)■記述家。1965年生まれ、新発田市出身。著書に、ルポ作品「新潟を有名にした七人の食人(しょくにん)」(新潟日報事業社刊)、「魚屋の基本」(ダイヤモンド社刊)、小説に「飛べ!ダコタ 銀翼の渡り鳥」(東邦出版刊)ほか。新潟清酒を題材にしたエッセイ、ラジオドラマの脚本も手がける。
連絡先 chemmy_wtb@yahoo.co.jp
comming soon
comming soon